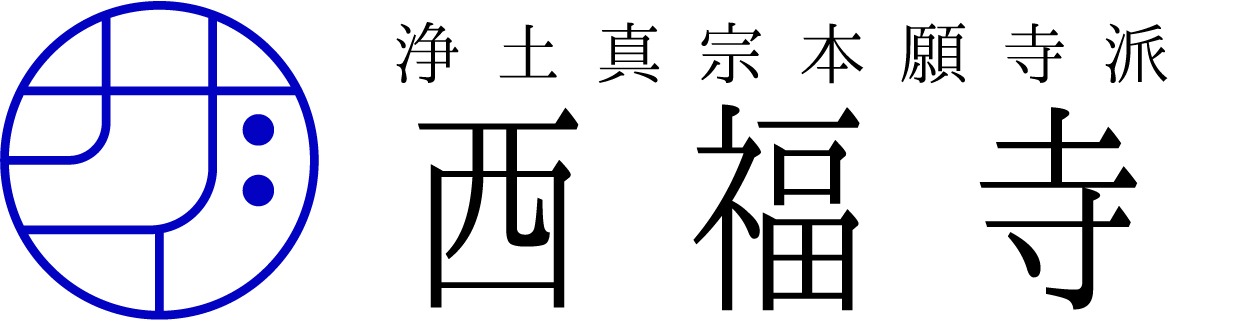『氷の解けるまで(6話)』大前しでん小説
「おい、そんな言い方無いだろう。仮にも俺は圭ちゃんの婿になる男なんだぜ」
「そりゃ、そうよ。決まってるじゃない。
そうね、人志君言い過ぎた。ごめんね」
「別にいいけど、いつも冷静な圭ちゃんがそこまでムキになるってことは、よっぽど深刻な問題だってことだよな。
でも、どんな状況でも娘が結婚することを本気で叱る親っているのかな?」
「叱ったりはしないわよ」
「私が勝手にあれこれ考えて不安がって思案してるだけよ。
でも、心配しないで日曜の事は先週の夜に伝えてあるし無愛想な返事だったけど時間は空けてくれるって言ってたから。
(四)刹那
今朝は、初秋を感じさせる群青が空一杯に広がり肌寒ささえ覚える。
圭子にとって心中複雑にして長くて不安な日曜が訪れた。
父の日曜の習慣と言えば何気ない数十分の散歩から始まって必ずお経を一巻上げて朝食を摂る。父は、一人っ子の私を三十歳で儲け、私が二十七歳なので父は五十七歳ということになる。
母さんは父より二歳年上でふっくらしたとっても温和で礼儀には厳しい人だった。
けれど、職人気質な父の性格が勝ってか母さんが父より年上とは私が物心付いた頃にでも信じることができなかった。
しかし、父が母さんに対して強烈に恋心を抱いていると思わせるエピソードが子供の頃の圭子の脳裏にひとつ残されていた。
私が小学五年生の頃、ピアノの習い事で帰宅が遅くなりそれを心配した母さんが咄嗟に常着のまま自転車に飛び乗って迎えに来てくれたことがあった。
その日は、夜から大きなボタン雪が深々と降り始めとっても寒かった。
雪は僅か一時間ほどでみるみると路面に積もっていった。
母さんと私は、自転車で片道十五分程度の農道を走って帰るのだけれど積雪が行く手を遮り敢え無くボタン雪の降りしきる中、自転車を押しながら帰ることになった。
それから、母さんが自宅を出て四十分ほどが過ぎた頃だろうか?正面から私達に近づいて来る一台の見覚えのあるバイクが近づいて来た。父だった。
上着を着て来なかった母さんを気遣って上下揃いの防寒着にマフラー、手袋を携えて現れた。その時の父のいでたちときたらバイクにも関わらず手袋もせず、上下薄っぺらな灰色の作業着だったことに驚いた。
そして、母さんに向かって一言いった。
「今から一時間しても帰ってこなかったら必ず助けに来てやるからな、安心しろよ」
二人して笑いながら焦って帰ったっけ。
< 続く >