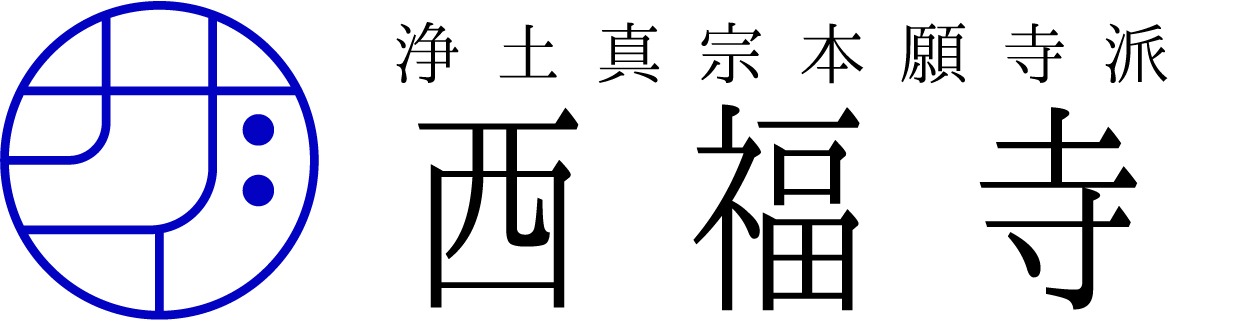『氷の解けるまで(4話)』大前しでん小説
(三)告白
「どうしたの圭ちゃん
今日は何だか浮かない表情してるよね?」
「人志君さぁ、来週の日曜が来るのが何だか怖いんでしょ?」
「圭ちゃん、どうしてそんなにお父さんのことが怖いの?正直、圭子の性格からは全く想像もつかなかったね」
「何よ、勝手に決めつけないでよ。私、まだ人志君に何も答えてないじゃない」
「だから、図星なんだよ」
「何よ、それって」
「プロポーズするような関係になっている男がね、彼女の話し出すイントロと表情ひとつで深層心理がよめないようでどうするのって話だからさぁ。
まぁ、いいさ。俺は行くよ。来週の日曜、本気だかんね」
「人志君たら、決まってるじゃない。この際、包み隠さず打ち明けとくけど私ね、お父さんが怖いとかじゃないのよ」
「じゃ、何なの」
「この件に関しては、私自身が逃げていて色んな言葉を探したけれど正直うしろめたいのよ。
私が中学二年生の時にね」
「お母さんは亡くなったって聴いたよ?」
「もう!ちょっと喋らせてよ!真剣なのよ」
「ごめん、ごめん」
「その事からずっとうしろめたいのよ。母さんが亡くなった理由は私なの」
「何故なの?」
「その日は私が、冬休みで母さんと年末の慌ただしい時期に無理を言って商店街のイルミネーションを眺めながら色んな話をしてショッピングに出掛けてたの。
私は数日前から少し気持ちが落ち込んで沈んでいたけれど母さんと話すうちに楽しくなってきて心が躍っていったことを今でも鮮明に記憶しているわ。
それで、クリスマスが近かずいていることもあってプレゼントをねだって買ってもらったのよ。
初めてのスマホだった。
それで私、気持ちが舞い上がっちゃって母さんに「歩きながら使っちゃダメよ」って注意されながらも触りながら歩道を歩いて帰っていたのよ。
その時、歩道を無視して猛スピードで突っ走って来たバイクが私の方に向かって進んで来て。
私はそれに気が付かずスマホに夢中で、それで母さんはとっさに私に覆い被さるようになってかばってくれた。
私はかすり傷ひとつ無く助かったけど、母さんが代わりに頭部を強打して意識不明になって救急車の中であっと言う間に息を引き取って逝ってしまったの。
私はその現実が信じられなくて、信じられなくて、ただひたすら泣いて泣いて。
それからは私の人生なんてどうでもいいと自暴自棄になって中学三年の時に自分の命を殺め母さんに謝りに行こうとした時だった。
死に方も解らずリストカットの真似事の結果病院に運ばれ病室のベッドの上で一度だけ父に頬を強く叩かれ諭されたことがあるの。
『死んで母さんに詫びるくらいなら、もっと生きたかった母さんの命をお父さんと二人で背負って一生掛けて倍の苦楽を味わい社会に貢献して詫びてみろ』ってね。
それから退院して何とか私は気持ちを少しずつ取り戻してはいけたけど次第に気が付くとお父さんの顔が正面から見れなくなっていた。
父もそれからは私に殆んど喋ってこなくなって」
「それで圭子は、今でもスマホをあまり触らないんだね、付き合った時からおかしいなって思ってたよ」
「私、トラウマなのよ」
「圭ちゃん、お父さんはそれからどうなったの?」
「今は、全然そうでもなくなったけど、あの頃は酷かったわ。
今、考えるとお父さんが荒れたのは私と話さなくなってからかもしれない。
働いてはいたけど仕事場での喧嘩が絶えることがなくなってお酒を泥酔いになるくらい毎晩飲んで公園のベンチで転がって頻繁に警察から連絡が入ったりしてね」
「ところで、その事故の詳しい真相のことお父さんは、知ってるの?
その原付バイクのことも問題だろ?」
「うん、私のことを含め相手の交通違反などは近くのコンビニの防犯カメラで証明され実況見聞と現場検証によってお父さんへ真実は白日の下にさらされたはず。
加害者との裁判などは父が全部対応してくれて私が高校一年の冬休みくらいには裁判所で判決が下ったことだけは知らせてくれたわ。
でも、詳しい結果を知ったところで母さんが戻ってくるはずもなく、私は一刻も早く事故の件は忘れたかった」
「するとそれから、十二年経つんだよな」
「でも、その判決が下ったその年の冬からお父さんは、益々私と一言も叱らなくなり愚痴やぼやきなんかも一切無いのよ。
またそれが余計に私にしたら辛くって。
それで、歳月を重ねるごとに無意識にお父さんの機嫌を気にするようになってね」
「解るよ、圭ちゃんの気持ち。だけど、それと来週俺が結婚の挨拶に行くことを怖がるのとどう関係があるのかな?」
< 続く >