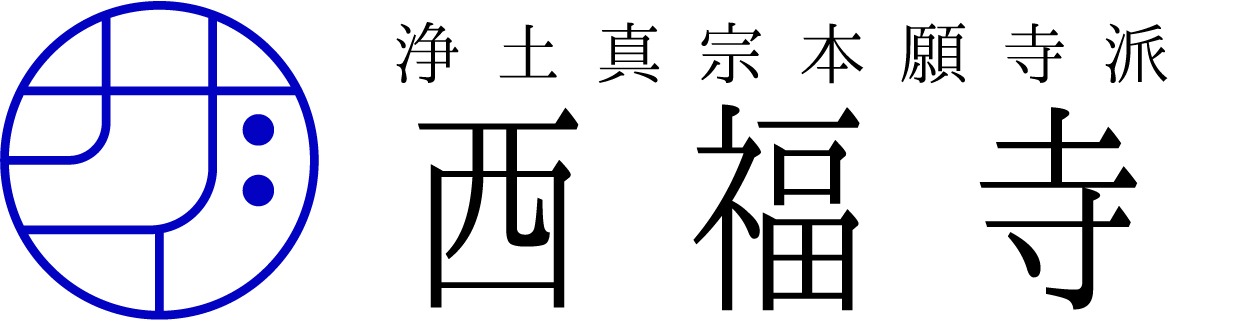『氷の解けるまで(2話)』大前しでん小説
㈡後悔
その夜、父の機嫌はあまり良くなかった。
父は帰宅すると一目散に仏間に入って必ずお参りをする。
父の機嫌はおりんの音色で概ね察するようになった。
あの日から圭子は、自分でも異常なほど神経質になっていたのだ。
いつもなら、その音はかんだかく澄んでいて心が穏やかに和むようなゆったりとした二つの音色であった。
けれど、今夜のそれは耳をつんざくような怒鳴り音のように大きく響き、そのうえ音と音の間隔がとても速やかった。
父のおりんの鳴り響く仏間には、眩しく光る黄金の塊で出来上がったような仏壇が睨みを利かせ屋敷の中央を陣取っている。
父は朝夕その塊の中にそっと祀られた母さんの魂と父の心との対話を何より楽しんでいることを密かに知っていた。
その時間は短い時には三分程度、長い時には三十分以上その都度父の気分によって異なるのだ。
圭子が想像するに、その対話は父がどんな深く悲しい相談を持ち掛けようと、どんなに腹を抱えるような愉快な話を語っても魂から発せられる声は一言も返って来ることなど無いと思っていた。
時に、母さんが大好きだったイチゴ大福に挽き立ての熱いコーヒーを用意して父が塊の前で屈託ない表情を露わに乾杯しては小声で何かを語り掛けるような音がする日がある。
いつだったか、塊に小さくうなずく仕草をしてみせる日もありその父の姿を襖の隙間からわずかに見えてしまう時がある。
そんなおとぎ話のような時間が過ぎ去った後に残るのは無言で交わした乾杯の後の一人で飲み切った空っぽの焼酎グラスとただ減らずに冷めていくだけのコーヒーカップそして、お皿には硬くて伸びなくなったイチゴ大福が虚しく残るだけだった。
< 続く >