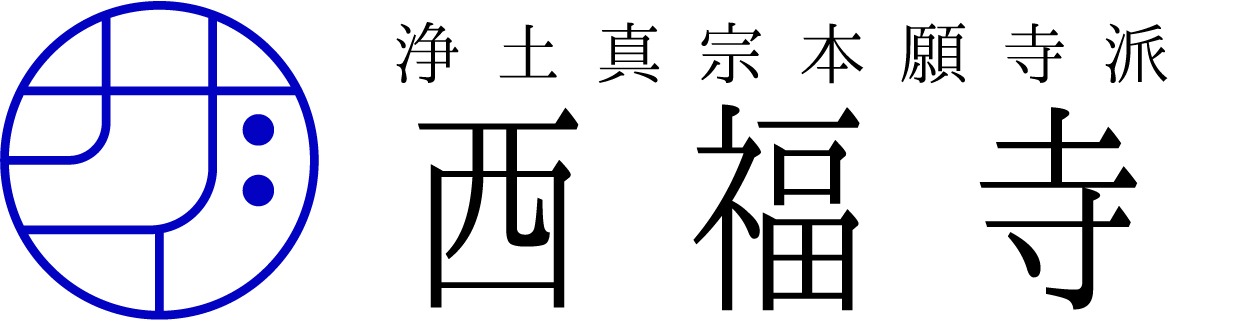『互いの面影(2話)』大前しでん小説
(2)ふれあい
通勤はいつも最寄り駅からの電車で家賃のことを最優先に考え駅までは徒歩で一五分と遠く、急行は停車せず郊外から少し離れた決して市民受けされることのない古びた場所からの通勤となることを承知のうえここを住まいに選んだ。
駅に着くと毎朝、必ずアンモニア臭が鼻をつく拠り所に立ち寄るのである。
そこには、閉まりきれずに傾いたままでいた木枠の窓が眼前を陣取り、それは摺りガラスで一部は割れて穴が空き、ひび割れの筋も無数に入っていた。
そこに夜半過ぎから、ちらつき始めた粉雪が少しでも暖を求めたかったのか?
忍び込んだ努力の証ともとれる僅かな積雪が窓際の隅にひっそりと影を潜めていた。
「いつもお世話になっております」
自分の生理現象といえ黄ばんだ小便器に
「自分も便器の黄ばみの共犯者」
と少し罪悪感を抱きながら幾ばくか反省し、心の中でお詫びの気持ちで敬礼してみせた。
ここでそうやって習慣儀礼のように用を足し電車に乗り込むのであった。
「おはようさん」
「あっ、おはようございます」
「今日も寒いわねぇ」
「そうですね、ここのところ、なかなか布団から出れなくて冬場は寝床から出てしまえば一日の大半の仕事が終わったような安堵感に包まれるんですよね」
「分かるわね、寒いの辛いし眠むしね、あと五分あと五分って布団にくるまり潜り込んじゃってね」
と普通の何気ない会話である。
そんな後、通勤の合間に何気なく考えた。
毎朝、この様な会話をしながら私はイチモツをあらわに溜まった小水を放出している。
その真っ最中にも関わらずアカの他人でしかも高齢とはいっても立派な女性が男子トイレに現れ何の躊躇もなく会話しているのだ。
しかし、私はその実、ここ何年もの間そのひと時の日常会話に楽しみと女性と出会える期待感を抱いていると言うといささか誤解が生じるかもしれないが、何とも心地良い安心感を覚えていたのだ。
それは、何か子供がようやくオムツが取れそうでお漏らしせぬよう傍らでお母さんがトイレの傍らより優しくエスコートしてくれているような、どことなくその会話を交わす光景と似ているように思えてくるのであった。
そして、そのおばさんの容姿はと言うと、
何度このトイレの床を踏みしめたことか?
決してお世辞にも綺麗とは言えないもので、
始めは純白だったはずのものが今では茶色にくすんでしまったスニーカー。
そして、町おこし恒例のゆるいキャラクターアニメをあしらった青色のエプロン。
両手には、紺色で手術用のようなピチピチのビニール手袋。
現代のご時世にそのようないでたちの女性が侵入しているのだが、その不可思議な現実を目の当たりにしても誰ひとりとして批判なんぞせず訴えることもない。
ここには、未だ男女平等だのセクハラだの堅苦しい概念はなく女性の本質である繊細で几帳面な側面を尊重した『トイレ清掃員』と言う職務の提供が毅然と存在するおおらかな国家であることを誇りに思い少し心の中が『ホッコリ』とする啓介がいた。
(つづく)