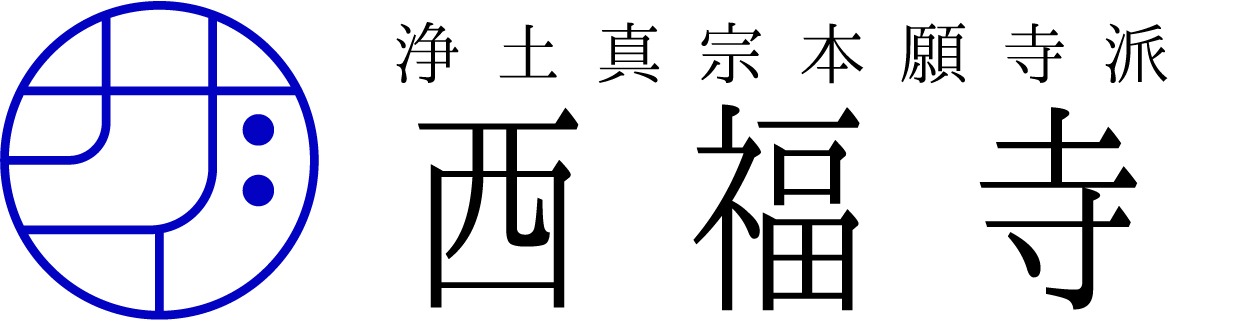『あの頃』大前しでん小説
かくれんぼ、缶蹴り、影踏み、案山子、マル書き、肉弾、ハンカチ落とし、あやとり。
幼ない頃の遊戯は素朴で随分と楽しかった。
たとえ勝っても何ひとつ懸賞など無いのにひたすら勝ちに拘って夕ご飯まで無心に遊んで遊んで遊びまくった。
それは楽しかった、とっても楽しかった。
昨日、あの頃一緒に遊んでいた向かいの家の健太が亡くなったとの連絡が入った。
その頃、健太は小学一年生で私が三年生だった。
ということは、五六歳で他界した事になる。
健太の家は私の自宅と道幅数メートルの小道を挟んだ斜め向かいに位置しており、互いに家族ぐるみの付き合いで親戚のようだった。
今、大声で泣きじゃくるおばちゃんの声がここまで薄っすら響いてくる。
あの頃のおばちゃんは三十代で若くて綺麗だった。
毎朝、毎朝笑顔一杯で健太のお見送り。
「健坊、気を付けるんだよ」
「ズボンからカッターシャツがはみ出てるわよ」なんて気遣ってた。
あの頃の優しいおばちゃんが今泣いている。
刻々とお通夜の時間が近づいてくる。
おばちゃんがチリ紙に包んで貰った、かりんとう、手作りでアンコが沢山入った大福餅、芯まで柔ら柔らくサクサクとしたかき餅。
何故だろう?
健太の思い出よりおばちゃんとの思い出が走馬灯のように過ぎていく。
樟脳臭い喪服に袖を通し、それから湿った生臭い革靴へ両足を押し込んだ。
内ポケットには、健太とおばちゃんと一緒に七夕会の短冊の横で並んで写った記念写真、
そして、少し大きめのハンカチを懐に。
息を止めてドアノブをひねり夕闇に身を委ねた。
すると、いちだんと泣き声が大きく響いてくる。
自宅でどうしてもお別れをしたかったのだろう?
健太の思い出がはみ出るほど、ぎゅうぎゅう詰めになったこの場所で。
俺は、この現実に腹がよじれるほどの怒りを感じ悲しくてたまらなかった。
そして、俺はここで決意する。
おばちゃんの打ちひしがれて傷んでしまった心と顔面をぐしょぐしょに泣き腫らし真っ赤に充血した瞳、それらと対面する勇気を振り絞るために。
俺は、我慢しない。
決して我慢なんかせず大声で泣いてやる。
おばちゃんと一緒になって俺も涙が枯れはてるまで泣いて泣いて泣きまくるのだ。
『健太、いつの日か!
また、遊そぼうな』
念う母 産湯と湯灌 子の三界