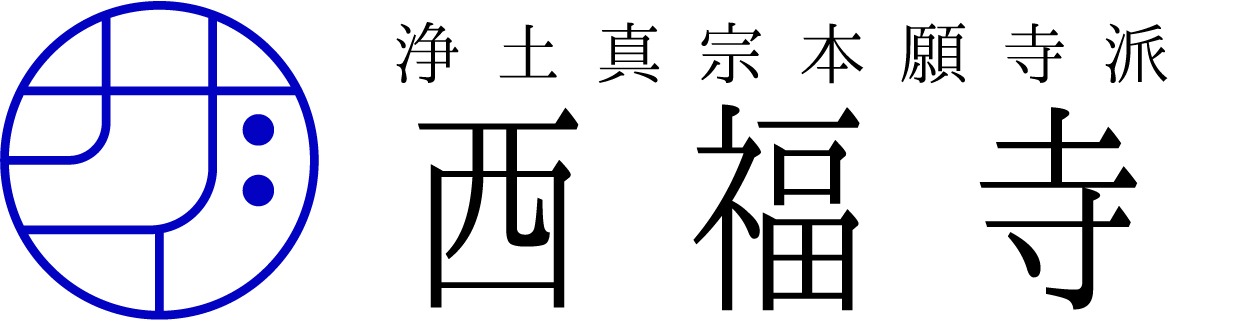『省かれた釈の字に』 読む法話 日常茶飯寺 vol.42
浄土真宗を開かれた親鸞聖人がお生まれになったのは1173年のことでした。お誕生日は今の私たちの暦で言うと5月21日であったとされています。今年はなんと、親鸞聖人がお生まれになってから850回目のお誕生日の年なのです。本山西本願寺をはじめ、世界中の各所で盛大に親鸞聖人のお誕生をお祝いする法要が勤まりました。
今号では改めて、親鸞聖人という人について書かせていただきたいと思います。

[写真]親鸞聖人像「熊皮の御影」
「親鸞聖人は生涯、鏡の前に座られたお方だった」とよく言われます。これは、死ぬまで身だしなみを気にされたオシャレさんだったということではありません。自分自身の内面から生涯目を逸らさなかった人ということです。
親鸞聖人はご自身の名を「愚禿釈親鸞(ぐとくしゃくしんらん)」と名告られましたが、沢山お書きになられたお書物の中でただ一箇所だけ、釈と親の二文字を抜いて「愚禿鸞(ぐとくらん)」と名告られた箇所があります。
省略されているこの「釈」という字は、法名に用いられる字です。
浄土真宗でいう「法名」というと「釈○○」と、頭に必ず「釈」がつきます(西福寺では「釈」の旧漢字の「釋」の字を用いています)。これはお釈迦さまの釈の字をいただくことで、仏弟子となり仏法を聞く者しての名前を意味します。(ちなみに私の法名は「釈智行」です。)
余談ですが、法名はご本山(西本願寺)で授かることができますのでご希望される方はお気軽にご相談ください。
親鸞聖人はあろうことか、その釈の字を省略されているのです。ここに親鸞聖人の痛切な思いが垣間見えます。
では、ただ一箇所だけ「愚禿鸞」と名告られた文章はどのような文章であるかを見ていきましょう。
「悲しきかな愚禿鸞、喜ぶべきものがもうすでに目の前に与えられていると聞かせていただいても、私というのはそれを喜ぼうともせず、欲にとらわれた自分勝手な生き方しかすることができません。そんな自分の愚かさ、闇の深さを思ったら、恥ずかしく、傷ましいことです」(住職私訳)
これは、親鸞聖人が自分自身が悲しいと嘆いておられる文章です。
自分自身の愚かさを嘆く場面で、ご自身の名から「釈」という字を省くことによって、「仏弟子を名告る資格など微塵もない私であった」という痛切な思いを込めておられます。ただ「釈」の字を省略するだけではお釈迦さまに対して失礼になる、という思いで親鸞の「親」の字も省略されたのかもしれません。
この背景にはきっと、比叡山で9歳から29歳までの20年間死にものぐるいで修行をなさった経験があったでしょう。比叡山では千日回峰行という命をかけた過酷な修行があって、1585年から今日までの438年の間で達成した人は51人しかいないそうです。親鸞聖人が千日回峰行をなさったかどうかという記録は残念ながら織田信長による比叡山焼き討ちによって焼失してしまい分かりません。けれども親鸞聖人の比叡山での立場と在籍年数から考えて、少なくとも2回は千日回峰行をされたのではないかと言われています。
ただ、親鸞聖人にとって何かを達成したとか成し遂げたとか、きっとそんなことはどうでもよくて、問題はただただ自分自身だったのです。命をかけた過酷な修行を経て目の当たりにしたのは、以前と何も変わらぬ欲にまみれた自分の姿だったのです。修行も満足に出来ない、仏道を歩むことさえ出来ない自分であった。その奈落の底に突き落とされるほどの悲しみを、仏弟子を意味する「釈」の字を省くことで表現されているのです。
そしてもう一つ注目したいのは、文章の最後に「傷ましい」という表現をされているところです。私たちは自分自身のことを「お恥ずかしいことです」と言うことはあっても「傷ましいことです」とはあまり誰も言わないのではないかと思います。
生きていく中で、自分が発端となって何かしらのトラブルになってしまうことがあります。誰かを傷つけてしまったり、怒らせてしまったり…。
そういう時私の心の中には、責任逃れをしようと自分以外に責任の所在を探したり、誰もが納得するような言い訳を探したりする、ずるい自分がいます。「それは仕方なかったね。あなたは悪くない」と言ってもらえるような言い訳はないだろうか。そんな時、嘘をついてしまおうかということさえも頭をよぎるのです。私の心の中は他人に見せられないことばかりです。そういう見せられない部分、自分でも全く意識したこともなかった心の黒い部分があらわになってしまった時にゾッとした経験はないでしょうか。そういう自分を見たくなくて、認めたくなくて、私は反射的に目を逸らしてきました。
でも親鸞聖人はそういう自分から目を逸らさなかった人です。宇宙のようにどこまでも深く果てがない自分自身の内面。その深淵を覗き続けたのが親鸞聖人だったのです。それは、ゾッとすることの連続だったことでしょう。自ら絶望に向かっていかれたと言っても過言ではありません。まさに常軌を逸した行為です。親鸞聖人はそういう自分自身との出遇いを「傷ましい」と表現されたのです。
親鸞聖人のお姿が描かれた「熊皮の御影(写真参照)」を見ても、どんなに傷みを伴っても決して自分の内面から目を逸らさない厳しさがお顔から滲み出ているように私には感じられて、胸が締め付けられるような思いを抱きます。
けれど、親鸞聖人は聞いたのです。仏弟子を名告る資格さえない自分を喚(よ)ぶ声を。我が身の傷ましさの全てを知り抜いた上で、「必ず救う」と喚んでくださる声を。その声こそ「南無阿弥陀仏」この一声のお念仏だったのです。
その喚び声を聞く中に「何者にもなる必要などなかった」と、生涯鏡の前に座られたのでした。
もし私たちが親鸞聖人に
「私は救われるのでしょうか」
と尋ねたならば、きっと親鸞聖人は笑顔でこうおっしゃるでしょう。
「この親鸞が救われるのですから」と。
合 掌
(2023年6月5日 発行)