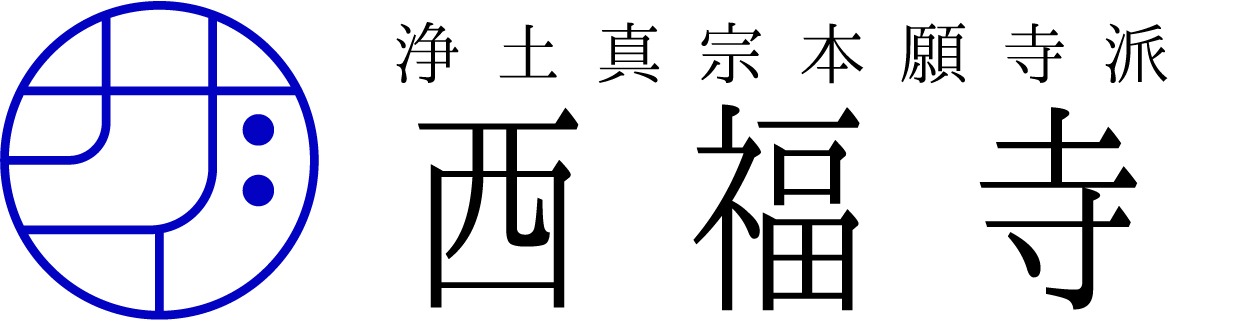『互いの面影(1話)』大前しでん小説
今朝も携帯電話の目覚まし音が地獄行きの合図のように激しく鳴り響いた。
私の魂は幻想的な世界に浮遊し続づけ現実逃避を毎晩繰り返していた。
私は、時間経過の速さが信じられず、その現実を真っ先に確かめようと少々まどろみながら長年、枕元で時を刻み続けている楕円形で木目調の電波時計に夢だと祈りながらぎこちなく細長い手で眼前まで握りしめては幾度も針の指す数字を見直すことが起床する前の常であった。
それからその現実を何とか受け入れると決まって、自分の体温がこしらえた煎餅布団の中で再び強く瞼を閉じるのであった。
その布団の中は、羊の体毛をあしらってできあがったウールの様に随分と居心地の良さを実感することができ、その時改めて
「自分は熱を放出し生きているのだ」
と実感するのであった。
そして、おおよそ五分くらいだろうか?
その中で虚像化した自分の中の天使と悪魔が交互に戯れるのであった。
そして、前夜に用意しておいた通勤着に素早く着替えるため精一杯の勇気を振り搾り、
心の中でゆっくりとカウントダウンを始めるのであった。
「男の一人暮らし」
それは、年齢を問わず孤独で増してやこんなに肌身に凍みる冬の朝ともなると心身共に冷え切ってしまい、その一時は決まって、あたかも世界中の不幸を自分が一人で背負い込んでいるような強い被害妄想を抱いてしまうぐらいの憂鬱と不安に苛まれてしまうのだが、そのくせ簡単にその峠が通り過ぎてしまうと自分は心の弱い人間であることを改めて自覚する啓介であった。
朝食といえば予めコンビニエンスストアで準備しておいた人参の少ないカップサラダ、小学時代から食べ続けている表面がやや硬めのメロンパンにホットコーヒーそれが定番であった。
それらをせわしく胃に流し込み、見繕いもほどほどに暖かい寝床の悪魔に後ろ髪を引かれては玄関先の革靴に靴ベラを押し当てた。
そしてようやく、ドアノブを手すると小さく錆びれた安っぽい音が「ギィー」と鳴り響きゆっくりとこじ開けるのである。
やっと啓介の魂が会社へ動き始めた。
(つづく)