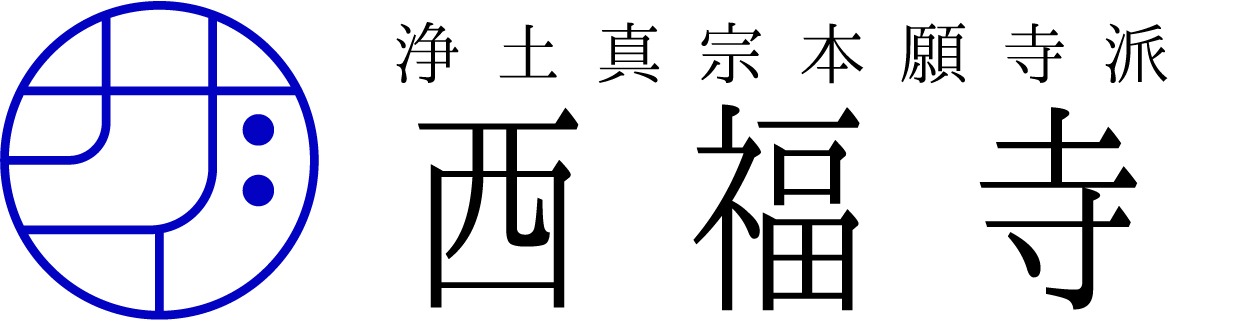『補助輪』大前しでん小説
「さぁー行くぞー。 怖がらずに真っ直ぐ行くんだぞ!」
ここ数週間は雨でも降らない限り日曜の午後になると良くんの自転車の稽古に明け暮れている家の主人。
「どれどれ、少しは進歩したかしら?」
良くんの自転車の右側にはいつも補助輪が付いていて転ばぬ先の杖になっている。
私は、その実直で微笑ましい二人の姿を眺めながらガラス細工のようで一度手を離してしまうと直ぐにぐちゃぐちゃになって壊れてしまいそうで。
そんな、途上の我が家の平和にも頑丈な補助輪が付けられたらいいのになぁ、なんて少しだけ羨ましげに良くんが乗る自転車姿を眺めていた。
「良くんの補助輪が取れる頃には、この街ともお別れだな」
この町並みが、この景色が、この匂いが、ここの人々が何もかも全部大好きだった。
時代の流れに左右される中堅企業のサラリーマンは常に会社都合の転勤と隣合わせだ。
生活のために働らいていた主人から働くために生活せざるを得なくなった主人の気持ちを考えると心が締め付けられる思いがする。
私と良くんそして、新しい命も一緒に貴方に乗っかって新しい街に行くからゆっくり、ゆっくり倒れないようエスコートしてね。
だって私達がこれから乗り続けようと決意している乗り物には立派な補助輪が付いるんですから。
それは、貴方の真心です。
そうだ、こんな事してられない。
早く新たに予約の入った同乗者の名前を決めんなきゃね。
やすらぎの 今を守りて 強がらん