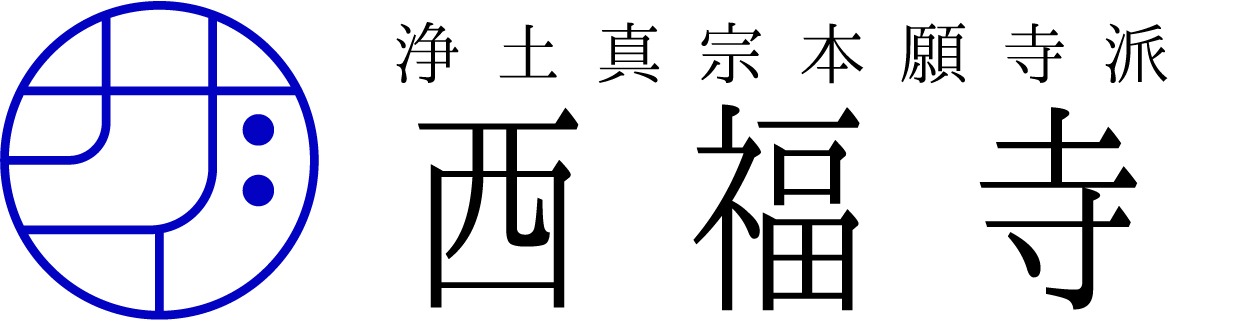『よすが』大前しでん小説
いつものように近所のスーパーに出掛ける冷えきった朝。まさしくいつもの朝である。
寒さで揺れて震える百年柿、それが一度も誰の口にされることもなく地べたに落ちて涙を溜めては腐っていく。
道端の水溜まりには、泥を含んだ薄氷が張り、今朝の登校児童の靴底に触れて無数のガラスの破片のように割れて散らかっている。
その中には尖っているものやデコボコなもの様々があって涙を流してる。
しかし、そこから少し離れると全く被害に遭わず難を逃れたものもあった。
それらは、恐らく大きな笑みを浮かべているのではないだろうか?
いずれにせよ、それらは、いつかは溶けて無くなるのだ。
そんな小汚い泥を含んだ薄氷にも素朴な心が宿っているような気がした。
そんな景色と自分がどうしょうもなく投影して被害を受けずにいる薄氷には今すぐ走って行ってこの足でぐちゃぐちゃに壊したくなった。
一方で枝にぶら下がって難を逃れようと必死に耐えこらえているものには、今すぐ走って行ってこの小汚ない、しわくちゃな手の平でもぎ取ってむしゃむしゃと噛み砕きさっさと胃におさめ成仏させたくなった。
人生とは選択の連続で時間は有限に過ぎていく。
後悔を繕う言葉「もし、たら、れば」が
大好きで大好きで。
人生はどんなに迷ってもどちらか一方しか選ぶことはできない。
どんなに財に恵まれてもどんなに才覚を備えようとも選択を誤った敗者が孤独でありながらそれを取り戻すには些か限界があるのだ。
人間は一人では決して取り戻せない。
最後はだれの瞳にも映り込むことのない 「縁因便」を頼り、救われることで生きる。
辛抱して努力してひたすら精一杯に祈って。
けれども、今日も生きる。
スーパーのチラシとポケットに入った僅かな小銭をよすがに。
もたれ合い 民見下さじ 欲制す